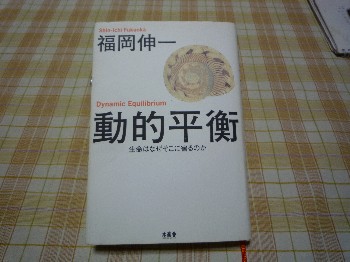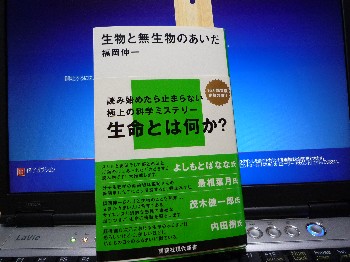今日は
午後まで諏訪の現場にいましたが
松本よりかなり冷え込むなー
と思っていたら
3時頃現場を出るときに
降り始めました
雪が・・・
クリスマスらしくなってきましたねえ
早めにタイヤを履き換えなければ
と思いながら帰ってくると
何やら楽しげなお二人さん
あさってのイベントに向けて
お片づけ&飾り付けの最終段階のようです
2階にはツリーが
ウ ム ム
いい感じではありませんか
世間のペースからすると
こういったもの飾るのもちょっと遅めですかね・・・
「リース作り教室」は
おかげさまで
定員いっぱいになりました
当日皆さんにお会いできるのを
楽しみにしています
昨日、おとといの諏訪での見学会にご来場
頂いた皆様ありがとうございました!
詳しいご報告はコダマチャンにお任せ
ということで(こちら)
今回も生物化学もの
またしても同じ著者 福岡 伸一氏
「動的平衡」 です
前回ご紹介した
「生物と無生物のあいだ」
でも主題として取り上げられた
シェーンハイマーの
「生命現象とは動的流れの中にある平衡状態である」
と言う定義をそのままタイトルにした本です
ワタシの好みだけの事かもしれませんが
この人は ”ホンモノ” 感があって
いいです
ちゃんとした
思考・思想の感じられる
物静かな雰囲気が文面からも感じられます
以前脱税のばれた
どっかの売れっ子脳科学者(?)とはチョット
違います
この本は
内容的にも前回のものよりかえって
分かりやすいと思うので
最初に読むならこっちのほうが
いいかもしれません
女性にも気になる
生物学者の目から見た
「ダイエットの科学」や
化粧品会社が怒りそうな
「ヒアルロン酸」を顔に塗りたくること
に関するお話なども
面白いです
「ミトコンドリア」は
体内にいる別の生物
とか
ノックアウトマウス
「えびす丸1号」
など 章別のタイトル見ただけでも
面白そうだとは思いませんか?
ついでに現在のワタシ達の生命観に
大きすぎる影響を与えた
やっぱり出ちゃった感のある
怪物(天才) ルネ・デカルト
(「デカルトの骨」なんて言う面白いノンフィクションもありますよ)
ワタシが1番面白かったのは
余談の様に書かれた話ですが
「なぜ大人になると時間が早く過ぎるのか?」
と言うよく出る話に関する
著者の考え
これって意外と答えだせない話で
実証のしようのない事柄だから仕方ないですが
今まで「そうかあ なるほど」
と言う意見はあまり聞いたことがありません
でも今回は
いい感じの答え
年をとるほど代謝速度が落ちる
→実際に感覚で感じる時間の経過は遅いはず
→子供の頃から進んでいる回りの時間は一定
よって
年をとるほど月日のたつのが早く感じられる
座布団 山盛り!!
って感じです
物理的時間と生物的時間の違い
納得です。。。
そう言えば・・・
昨日 H様邸で話していた時
「松中さん忙しいね バレーボールにも出てたじゃん」
「は・・???」
聞けばワタシに似た選手がいたとか
この方だそうです

バレーボール日本代表
八子選手
似てますか?
自分では全然似てるとは思わないのですが・・・
それにしても男子バレーはふがいないですね
女子は面白かったのになあ・・・
こちらは、H様邸のアイドル
以前にも登場したことのある
NANAちゃん
なんとも愛くるしいですなあ
今日は クロス張替&メンテの日
朝から、梓川 H様邸へお邪魔しました
壁と天井のクロスのクラックの補修と
部分的な張替工事
段取りの確認と
「松本市住宅リフォーム助成金」
の申請に必要な写真と書類に
ハンコを頂きに行ってきました
生活されている中での工事なので
かなりご迷惑をおかけしてしまいます
クロスをはがしているところ
せっかくなので
ブログ上で
「お施主様宅見学会」的に生活している
感じを写真アップさせてくださいとお願い
してみましたが・・・
NGでした (残念・・)
午後は
北深志 U様邸へ
1年点検へ
大きな問題はなかったのですが
2階で風の強い日に細かな振動音がするとのこと
今日もしばらく待っていたら
一瞬だけ鳴ったのですが
原因が特定できず
また風の強い日にいろいろ試して頂くよう
お願いしてきました。
クロスの補修については
年明けにうかがう予定です
会うたび 大きくなっていくご兄弟ですが
今日はお兄ちゃんのFくんは
風邪で調子が悪かったようです
いっぱい食べて
早く元気になるんだぞ~~
今回は 生物化学ものです
最近、本屋さんへ行っても
これ読みたいって言う本にめぐりあう事がトンと少なくなって
手持のものを読み返すことが多くなっています
そんな中でこれもかなり印象に残っているもの
読みながら考えるのが面白い本ってありますよね
そんな本の一つ
「生物と無生物のあいだ」
著者:福岡 伸一 (講談社現代新書)
「生命とは何か?」
「生物と無生物の違いとは?」
この問に対する考察を
近現代の細胞生物学の実験やエピソードとともに分かりやすく
考えやすく、学者とは思えないちょっと詩的な文も交えながら描かれています。
野口 英世やDNAの2重螺旋構造を発見した
ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリック
などなどその他にも色んな学者の人となりや発見に至る経緯なんかも詳しく書かれていて面白いですよ
機会論的な生命観では説明しきれない生命の不思議
細胞と言うミクロな視点で見るとその不思議は
・・・ホントに不思議??
ねずみを使った実験で
たったの3日でそのねずみを構成していた
身体のタンパク質は食事でえたアミノ酸の
約半数によって入れ替わってしまう!!
姿を変えずに中身がいれ変わる!
もちろん私たちもですよ
常に常に分解と合成がものすごいスピードで
繰り返され
肉体は入れ替わってしまう
臓器はもちろんたまっていると思われている
脂肪でさえもです
シェーンハイマーという学者がこの事を発見して
それまで
「生命とは自己複製を行うシステムである」
と言う機械論的な定義から
「生命とは動的平衡にある流れである」
と言う定義へ
なるほど!!
「シュレーディンガーの猫」で有名な物理学者の
エルビン・シュレーディンガーの問
「なぜ原子はそんなに小さいのか → 我々の体は原子に比べてなぜそんなに大きくなければならないのか?」
「なぜ、生命は絶え間なく壊され続けながらも、もとの平衡を維持する事が出来るのか?」
など、面白くも深遠な問が次々に出てきます。
後半のほうで著者は
自分達の体を構成するタンパク質などの
種類や数の表現について
「天文学的数字(この表現も正確ではない。これこそを生物学的数字と言うべきなのだ)」
と言っています。
これまでの内容を読んできて、
自分の体の中で
自分の知らないうちに
繰り返される生命現象
そしてその数と
宇宙を面白がって比較しながらいたワタシは
「先生、もしかしたら おんなじことかもよ」
とつぶやいちゃいました・・・
もういっこUPしてま~す
⇓