水土里ネット おおまちからのお知らせ
イベントのご案内やイベント報告などをお伝えします。|
今年の「米作り体験」第1段となる「種まき作業」は、天候もよく桜の花も開花し、優しい日差しが射す、穏やかな陽気の中で行われました。  説明を聞いたら次は、児童達自らの手での作業となります。3人一組で協力して、種まき作業が行われました。 まず苗箱に床土を敷きならし、たっぷりの水を注ぎます。  次に種もみをまき、殺菌液をかけ、覆土で種を覆います。児童たちは、先ほどの説明を思い出しながら、ゆっくりと丁寧に作業を行っていました。  そして最後に、出来上がった苗箱をハウスに運び、「種まき作業」は完了となります。作業全体を通して、丁寧に作業を行う児童たちの姿がとても印象的でした。  2箱目の種まき作業を行う児童たちは、すぐに手慣れた感じで作業を進めていて、頼もしさを感じることもできました。 これから約1週間で発芽します。「米作り」の大変さや、「農業用水」の大切さを理解してもらい、今年も無事に秋の収穫が迎えられるよう願いつつ、児童たちの「米作り体験」をサポートしていきたいと思います。 |
|
|
この絵画展は農林水産省、文部科学省、環境省をはじめとした省庁等の後援、企業・団体の協賛を得て開催しており、本年度は全国より5,224点の応募作品が寄せられました。水土里ネットおおまち管内からは、49点の作品を応募し、厳正なる審査の結果、大町西小学校の小日向咲良さんと黒岩楠希さん2名の作品が受賞されました。  受賞した児童たちは、市長や記者の方から質問を受けたりと少し緊張した面持ちでしたが、しっかり受け答えをし、授賞を喜んでいるようでした。  ~受賞作品~ 「 初稲かり 」 小日向咲良さん  「 稲に囲まれた私 」 黒岩楠希さん  (受賞作品は「東京美術館」にて展示されました。) この絵画展を通じて、制作に携わった子供たちはもちろん、父兄やご指導いただいた先生方、また作品を見た多くの方々にもふるさとのすばらしさを発見し、水と土への関心を高めてもらうとともに、農業・農村の魅力をアピールすることを趣旨とし毎年開催されています。 |
|
|
11月29日、米作り体験最後を飾る「収穫祭」が大町西小学校5年生により行われました。11月中旬、児童たち手作りの招待状をいただき、参加させていただくこととなりました。  開催当日、学校に着くと、校長先生が迎えてくださり、開催時間まで応対してくださいました。すると、校長室まで児童たちが迎えに来て、「収穫祭」会場まで案内してくれました。会場には保護者の方々もいらっしゃり、温かく迎えていただきました。  席に着くと机の上にはおもち3種(ごま、きなこ、あんこ)と豚汁が用意してあり、丁寧なおもてなしを受ける中、いよいよ「収穫祭」が始まりました。 開会あいさつ、来賓紹介などの司会進行も児童たちが行い、一通り進行すると、「手を合わせて、いただきます。」 おもちはとてもおいしく ついてあり、豚汁もおいしく、お替りをさせていただきました。  「収穫祭」では児童たちによる学習発表も行われ、児童たちが学んだことや思いに触れることができ、大変楽しいひと時となりました。 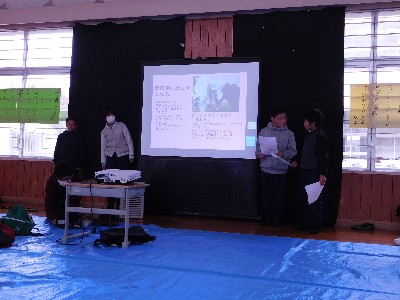 今年4月の種まきから始まった「米作り体験」、この「収穫祭」を迎えるまで、児童たちの一生懸命に作業を行う姿、また挑戦する姿を見て未来への頼もしさを感じました。児童達にはこの経験を通して、一緒に作業した仲間や先生、見えないところで色々協力し支えてくれた地元の方や保護者への感謝の思い、またこのおいしい もち米を実らせた農業用水や土といった自然を大切にする思いを、心のどこかにいつまでも持ち続けてもらえればと願います。 |
|
|
少し肌寒い10月15日火曜日の午後、「米作り体験」終盤となる脱穀作業が行われました。今年の作業では、脱穀機械を貸してくださり、機械操作も行ってくれる海川さんと、半年間に渡り様々な水田管理を行ってくれた平林さん、このお二人のご協力のもと作業を行いました。  作業の流れは、ハゼかけ棒から稲を機械まで運ぶ人、機械で脱穀された藁を運び束ねる人に分かれて作業を行いました。脱穀前の稲を運ぶ児童たちは、「お願いします!」と元気よく言いながら、海川さんに手渡していました。   作業も順調に進み、児童たちは水土里ネット職員協力の下、ハゼかけ棒の撤収作業も行いました。長い竹を運ぶときは苦労しているようでした。  続いて、平林さんが用意してくれた細かく切られた藁を、田んぼに撒き散らします。この藁は肥料となり、来年また順調にお米が育つよう、児童たちが撒いてくれました。  最後に収穫したもち米と記念撮影。  もち米の乾燥が少し足りないので、もみの天日干し作業と、精米作業を児童と先生たちで行います。  我々のお手伝いもこの脱穀作業で終了となります。4月の種まきから始まり、児童たち自らの手と、地元の土・人・水で実らすことができたこの「米作り体験」、その大変さや楽しさ、また大切さを知るきっかけとなれば幸いです。 |
|
|
北海道の黒岳では初雪が観測された令和元年9月19日に、大町西小学校5年生の「総合学習」である「米作り体験・稲刈り作業」が行われました。  それでは令和の時代になって初となる、大町西小学校5年生による「稲刈り作業」の様子を見ていきましょう! まずは稲刈りの作業方法について、当水土里ネット職員より説明を受けました。作業では鎌を使うため、その扱いには十分注意するよう、児童たちも注意深く聞いていました。  説明が終わり、いよいよ作業開始です!稲を刈る児童、稲を束ねる児童、それぞれが作業を分担し、また交替しながら作業を進めていました。    続いて、「はぜ掛け作業」です。田んぼの持ち主である平林さんが、稲を掛けられるように、はぜを事前に組んでおいてくれました。そのおかげもあり、順調に作業を行うことができ、児童たちは一つ一つ束ねた稲を丁寧に、そしてしっかりと、はぜ掛け棒に掛けていきました。  今では少し珍しいはぜ掛け風景。天候にもよりますが、2週間から3週間程度、自然乾燥を行います。  朝9時から行った稲刈り作業でしたが、鎌を使った作業ではケガもなくあっという間にお昼になりました。少し残った稲のはぜ掛けや落穂ひろいは給食後に行うとのことで、我々は帰庁させていただきました。 次回はついに「米作り体験」最後の作業、「脱穀作業」となります! |
|
Copyright(C) 2006 Midorinet Omachi. All Rights Reserved.
[
ログイン
]

