カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>
今回の軽井沢滞在中に行った中で、個人的な“軽井沢グルメ”のご紹介です。
先ずは、これまで希望しながらも一度も来られなかった、念願の「御厨」の朝食を食べに皆で出掛けました。
「御厨」は『里山のふもとで、かまどの煙突から煙がもくもく「田舎のおばあちゃん家に帰って来た」と感じて頂けるお店を作っております。薪をくべてかまどでお米を炊き上げます。地元の食材と一緒においしい朝食や昼食を楽しめる』古民家を改装した農家レストランとのこと。
以前は朝から人気の行列店だったのですが、今年の4月より予約のみに変更されたとのことで、大分前に娘の希望を受けて、家内が週末を避けて平日のこの日の朝7:45に予約をしてありました。
婿殿の軽井沢滞在が予定より一日短くなり、この日の軽井沢入りが9時で予約時間に間には合わず、しかし予約変更も難しかったことからそのまま一名減で伺うことにしました。

聞けばこの「御厨」は、東信地区を中心に松本店も含めて現在4店舗を展開するベーカリー「Cocorade(ココラデ)」を手掛ける、小諸市が本拠の「(株)あんでーくっく」という会社が運営する農家レストランで、この会社は元々は給食事業やお弁当からスタートしたのだそうです。

予約時間の7:45分の少し前に着くと、7時15分からのスタートということで、既に駐車場は殆どが県外車で、数台分を残して一杯。何とか苦労してアルファードを停めて、案内されたのは土間の椅子席ではなく、靴を脱いで土間から上がる座敷のテーブル席。
子供用の小さな椅子も用意してくださり、子供は無料で、きっと一番出汁を取った後の鰹節を使ったであろう、自家製のカツオのふりかけとご飯とお味噌汁を用意いただけるとのことで、合わせて子供用にだし巻き玉子と男爵芋のコロッケもオーダー。
大人は、私と娘が玉子かけごはん(1620円)、奥さまはとろろ汁膳(1680円)を注文しました。

私たちより先でほぼ同時に入られた隣のテーブルの家族連れに対し、先にこちらに注文伺いに来られてから、「あっ、そちらの方がお先でしたかね」と言われて先に対応をされるなど、店としての応対もキチンとしています。
土間から上がる板の間の小上がりには囲炉裏がしつらえられていて、土間から続く勝手場には昔懐かしいかまどが何台か並んでいて、薪と鉄窯で盛んに御厨の目玉であるかまど炊きのご飯が炊かれています。

大人用の朝食のかまどで炊いたご飯は、昔懐かしいおひつに入れられて食卓へ。農業も手掛けるという会社が、隣の田んぼ等で合鴨農法で育てたというお米をかまどで炊いたご飯。
当然期待していたのですが、ところが何だか変・・・。
というのも、粒立っていない・・・、ツヤツヤしていない・・・、べちゃっと米粒がくっ付いている・・・・。これって、何だかオカシイ・・・。

何年も専門でやっていれば、「始めチョロチョロ、中パッパ、赤子泣いても蓋取るな!」に代表される様な、それこそ昔のかまどの在る家庭では当たり前だった“かまどでの炊き方”には精通して熟知している筈で、間違える筈もありません。
少なくとも斯く言う私メも、生まれた江戸期からの茅葺の家で、それこそ亡きお婆ちゃんから「米一粒だって、お百姓が一年間丹精込めて育てなきゃ採れないだで、無駄にしちゃいけんゾ!」と言われて育ち、我が家の田んぼで採れた天日干しのお米で、後年薪で炊くのは大変なので電気釜に代わりましたが、それこそ幼少期には未だかまどで炊いたご飯が当たり前だったので(かと言って、必ずしも米の味には然程私自身はウルサク無いのですが)、イヤが応でも、子供の頃毎日食べたこの舌が間違える筈もありません。ですので、思うのです、これは一体何故なのか、と・・・???

一棟貸しで最大8名の4部屋ある別館の離れを含めても僅か9室限定のため、時間を掛けてゆったりと食事を楽しめる「金宇館」と、片や60席の「御厨」では根本的に運営における「おもてなし」の発想が違うのかもしれません。
人気店故に、「御厨」では15分毎に設定された予約時間で、テーブルに着いてから50分間という時間制限があり、次から次へと予約されたお客さんが訪れ、その途中に予約せずに飛び込みでのお客さんも来られます。
「今なら、40分後にはお席が用意出来ますが・・・」
と言われて諦める人や、「じゃぁ・・・」と言って付近を散策しながら外で待つ人たちも・・・。
それこそ常に満席のお客さんの対応に、スタッフの皆さんはお膳を抱えて走り回っています。
ですので、もしかするとかまどの“炊き立て”のご飯が常に供されるのではなく、客を待たせること無くすぐにおひつを運ぶためには、数十分毎にかまどで炊き上がったご飯を冷めぬ様にジャーで保温して、客の回転を良くするべく、客を待たせずに時間を置かずにそこから次々とおひつにご飯をよそって、準備が出来たお膳のおかずと一緒に運んでいるのではないか・・・?
その結果、運良く炊き立てのご飯が運ばて来る客さんと、タイミングによっては最後に残った大分前に炊き上がったご飯が運悪く供される客もあるのではないか・・・???
だからこそ、こんなツヤの無い、粒立たず、ずっと保温をしていた様なべちゃっとしているご飯になってしまったのではないか・・・???
・・・としか考えられないのです。
例えば、“米料亭”という看板を掲げる京都祇園の「八代目儀兵衛」は、客の注文後に一釜ずつ炊き上げる土鍋ご飯で知られていますが、そのご飯は炊き上がりから10分以上経つと客には提供しないのだそうです。そこまでご飯にこだわりを持つ料理屋さんも、現に存在するのです。
では「八代目儀兵衛」が“高級料亭”かというと、昼のコース(朝食提供は無し)の中の、三種の焼き魚御膳と鰆の照り焼き御膳はどちらも1980円(税込)で、御厨の昼のコースとそう変わりません。
ご飯の他にも、「御厨」の今回の朝食の中で期待したTKGの卵も、確かに橙色は多少濃い目かもしれませんが、黄身だけを箸で摘んで持ち上げられる様な特別なタマゴではなく、個人的には地場のスーパーでも買える様な(味も)“極普通”のタマゴでした。
しかし、お膳の中の一品に付いてきた男爵イモのコロッケは衣がサクサクしていて、揚げたての中身はほっこりで大変美味しかったですし、そして出汁の良く効いた豚汁も具だくさんでとても美味しくて、出来ればお代わりしたいくらいでした。そして家内の頼んだとろろ汁膳の焼き鮭も、甘塩で大変おいしかったそうです。どの料理も、決して高価な食材ではありませんが、キチンと丁寧に調理されていることが分かります。だからこそ、一番の目玉である筈のかまど炊きご飯が一体どうして?・・・と思わざるを得ないのです。
因みに、この日の朝食メニューは次の通りで、この日の小鉢は、優しい味のきんぴらごぼうでした。
・「朝のとろろ汁膳」・・・¥1,680
とろろ汁(信州味噌仕立て)焼き鮭・湯豆腐・小鉢・豚汁・香の物
・「卵かけご飯セット」・・・¥1,620
生卵・男爵芋のコロッケ・湯豆腐・小鉢・豚汁・香の物
・「朝の鯖味噌膳」・・・¥1,780
鯖味噌煮・野沢の菜天ぷら・湯豆腐・小鉢・豚汁・香の物

しかし一方で、スタッフの皆さんの対応は実に気持ち良く、帰りがけ厨房の写真撮影の可否をお聞きしたところ、気持ち良くOK頂きました。
そうした実際に目にした割烹着のスタッフ(地元のご婦人風)の皆さんの応対ぶりや、ニコニコとした働きぶりや、そしてこれまでの口コミの評判や、更には建物や周囲の雰囲気も(特に都会から来られた方にとっては)素敵に感じただけに、そして地元の信州人である我々でさえ楽しみにしていただけに、今回は本当に裏切られた様な気持ちでとても残念でした。ですので、むしろ失礼を承知で、敢えて本ブログに書かせていただきたく思うのです。
我々が訪れたこの日が、どうか“たまたま”の偶然だったことを願います。そして、どんなに人気店になったとしても、決して手間や時間を惜しまず、スタート当初の純粋な気持ちや方法を変えずに、これからも愚直に対応され続けられんことを願います。
そうでないと、当初はコスパも味も良かった松本の深志高校近くのイタリアンが評判を呼び、その後5店舗にまでに業態も含め拡大した結果、スタッフの応対も味も落ち、我々一家がもう二度と行かなくなってしまった店があるのですが、そんな店の二の舞になることは必定です。
ですので、どうか例えどんなに手間暇が掛かって大変であったとしても、是非頑張ってスタート時の本来の味を愚直に守って行って頂きたいと思うのです。
蛇足ながら、正直「御厨」での朝食を今回とても楽しみにしてからこそのガッカリであり、もしかすると私たちのこのガッカリは、或る意味これ迄の期待が膨らみ過ぎて、その期待が余りに大きく成り過ぎていた結果だったのかもしれません。だから、「そうだったんだよネー!」くらいに“軽く”思いたい・・・。
しかし、そうした期待が大きかったが故に、仮に今回の我々がたまたま運の悪い、万が一の偶然のタイミングだったとしても、今後軽井沢に来ても、もう二度とこの「御厨」に来ることは無いだろうと思ったのも、残念ながら事実なのです。
しかし、これは決してへそ曲がりの私メだけではなく、食べた結果の我々夫婦と娘も共通した認識であり、それ程までに今回は本当に残念に感じたのでした。
ですので、我々はもう関係ありませんが、どうか県外からの今後のお客様に対して失望させることの無い様に改善を切に期待します。
お盆の帰省に合わせた、次女一家の2週間近い松本滞在。
横浜に帰るのにあずさよりも新幹線の方が早くて楽なことから、最後に二泊三日で、いつもの軽井沢のドッグビラに行くことにしました。
勿論事前に予約をしてあり、結果的に婿殿は直接横浜から新幹線で軽井沢合流となったのですが、皆で松本から車一台で移動出来る様にと、事前に松本のトヨタレンタカーで8人乗りの新型アルファードを3日間予約してありました。
当日の朝、トヨタレンタカーの松本駅前店に行って手続きをして、乗る前にシートアレンジの遣り方を教えて貰ってから、マンションへ一旦乗って帰ります。アルファードは意外とショートノーズで、何よりもドライビングポジションがSUV並みに高いので見晴らしが良く、思った以上に運転がし易く感じます。ただ如何せん長い・・・。それもその筈で、アルファードは全長が4995mm(5メートル!)、全幅は1850mmで、コンパクトで運転がし易いからと家内が気に入った我が家のQ2の4200×1795に比べて、特に全長が80㎝も長い・・・。そこで慎重に慣らし運転を兼ねてマンションに戻ります。
その上でチャイルドシート2席、ベビーカー、ドッグカート各一台と、軽井沢から次女の家に宅配で送る段ボール箱とスーツケースなどの大量の荷物、更に大人三人とワンコ二匹・・・。どうやれば全部積めて人間が座れるのか???
あぁでもない、こうでもない・・・と色々シートアレンジを試しながら、何とか荷物を全部積み終わり、人間もしっかり座って、助手席の足元に敷いたペット用クーリングベットにワンコも載せて、いざ出発です。
トヨタのナビには慣れていないので、行先案内もACCも未設定。乗ってから、ナビ担当の奥さまが助手席で使い方をネット検索しましたが、スマホと連動させているQ2のナビとは異なり、結果的に運転中は(停止中でないと)設定不能でした。
しかし目的地には何度も行っているので、道路案内が無くとも全く問題はありませんし、まだ近間の軽井沢だからイイのですが、オートクルーズが使えないのは些か足が疲れました。この日はカーブの続く三才山峠経由ではなく、高速道路の長野道から上信越道経由で軽井沢ICを目指します。
慣れない車なので安全運転に徹し、軽井沢ICを降りてからもいつものカーブの多い脇道は使わずに走りましたが、予定通りの1時間半で目的地のアウトレット(軽井沢プリンスショッピングプラザ)へ到着しました。お盆開けの平日とはいえ夏休み中ですし、更にインバウンドでかなり混んでいます。
我々はこうした混む時の軽井沢は避けて、これまでこの時期には来たことがありませんでしたが、孫たちの幼稚園の夏休みに合わせての今回の帰省ですので致し方ありません。

その間に、子供と女性陣がフードコートからランチを買って来て、最後に私がフードコートに買いに行きました。ここでは“美味しさ”を余り求めてはいけません。しかもこの猛暑の日本列島で、本来エアコンの無くとも凌げる筈の涼しい軽井沢も今年は連日30℃超えで、この日の最高気温は33℃予想とか・・・。別荘族の皆さんも呆れる程で、これではもはや避暑に来たとは言えせん(ただ、軽井沢はさすがに朝晩は20℃以下になりますので涼しく感じますし、都会から来ると信州は湿度が低く、カラッとしていると感じるそうです)。
それから我々がワンコと子供たちを見ている間に娘は行きたいお店を回りましたが、結局まだ決められないとのことで、そのため我々が孫たちとワンコを連れて先にドッグビラに行って先にチェックインをして、娘がアウトレットでの自身の買い物と、この日の夕飯は移動で疲れたので外食ではなくテイクアウトして部屋食で済ませることにして、我々は明治亭のお弁当を娘にリクエストして、私がその頃またアウトレットまで車で娘を迎えに来ることにしましたが、そのお陰で娘も自分たちの欲しいモノが買えた様でした。

そして指定された午後3時半に迎えに行くと、昨秋に行った「白樺湖ファミリーランド」では怖がって、公園内を走る機関車トレイン以外何もアトラクションには乗らなかった上の子が、今度はしっかりとメリーゴーランドや観覧車など色んなアトラクションを楽しんで利用出来たのだとか。最低5つ以上乗らないと3300円(大人、2歳以上の子供は3100円)のフリーパスの元が取れないのだそうですが、今回は十分に元が取れたと娘たちは喜んでいました。そんな僅か半年での孫たちの成長ぶりに驚きます。帰りは浅間山がくっきりと全容を現し、その雄大さが感じながらまた「鬼押しハイウェイ」を走ります。
それにしても、途中浅間山の噴火に依って誕生した鬼押し出しという景勝地があるとはいえ、軽井沢から30分も離れ、途中有料道路(片道計650円!)に入るまでは九十九折の山道をずっと走らされて、軽井沢とは名ばかりの“北軽井沢”という山の中にあるというのに、ここだけは家族連れで結構な人気ぶり。
因みに「鬼押し出し園」も“北軽井沢”の開発やこの「おもちゃ王国」も、軽井沢の不動産開発も手掛けた嘗ての子会社「国土計画」に依る西武グループの運営であり、いくらその投下資本に依る設備の充実ぶりが違うとはいえ、「チロルの森」とのこの格差が一体どこから来るのか考えさせられた次第です。

 途中、その名の「白糸の滝」付近へ下って来ると、少し離れた駐車場にはまだ空きがあったので、娘夫婦はまだ見たことが無いということからそこに駐車。昔見たことがある我々がぐっすり寝ている子供たちと車で待っている間に、娘夫婦は歩いて「白糸の滝」を見に出掛けました。
途中、その名の「白糸の滝」付近へ下って来ると、少し離れた駐車場にはまだ空きがあったので、娘夫婦はまだ見たことが無いということからそこに駐車。昔見たことがある我々がぐっすり寝ている子供たちと車で待っている間に、娘夫婦は歩いて「白糸の滝」を見に出掛けました。有名な静岡の「白糸の滝」に比べれば半分ほどのスケールですが、幅70m、落差3mの軽井沢の「白糸の滝」はマイナスイオン一杯で涼しくて、“避暑地”軽井沢を実感出来たようです。
「白糸の滝」も軽井沢の観光スポットではあるのですが、下の駐車場は満車で人も一杯。夏の軽井沢はどこへ行っても混んでいます(写真は15年前に「白糸の滝」に初めて来た時と、同じく10年前に来た時のモノを使用しました)。
更に下って、次に重要文化財「旧三笠ホテル」横に停車。今秋の再オープンに向けて現在は改装工事で閉館中のため、外観だけを見学。確かに以前見学した時よりも塗り直されて外観がキレイになっていました。
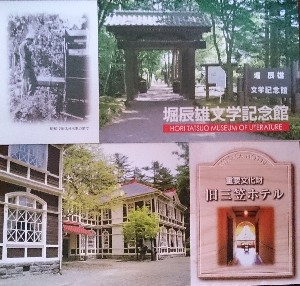

その後旧軽銀座を通り、この日の夕食を予約してある中軽の星野リゾートが運営する「ハルニレテラス」へ向かいました。

最終日、旧軽のロータリー近くのレストランで如何にも軽井沢らしいランチを済ませてから、横浜に戻る次女夫婦一家を軽井沢駅に送ります。
当日、町内は交通規制されているとの道路案内が出ていましたが、軽井沢駅には私服含めた警察官や報道関係者などたくさんの方々がおられ、この日、軽井沢縁の上皇陛下ご夫妻が電車で恒例の軽井沢への静養に来られるとのこと。
改札前がお出迎えの一般の方々も含めて混雑する中、孫たちは何度も振り返っては手を振りながらホームへと消えて行きました。
「ありがとネ!またおいでヨネ!!」
その一時間後、きっと「お帰りなさい!」という、軽井沢の地元の皆さんから上皇ご夫妻への歓迎の声が駅舎の中に響いているであろう頃、そう言えば15年前、お二人の出会いの場となったテニスコート近くの喫茶店で、マスターの奥さま曰く、
「お二人のテニスは、美智子さまの方がとっても攻撃的なのヨネ!」
と仰られていたのを懐かしく思い出しながら、我々は一足先に駅舎を離れてアルファードで松本へ向かいました。
途中上信越道の工事渋滞もあり、予定時刻をオーバーしてしまいましたが、最後の最後まで安全運転で無事松本へ到着し、最後に車を返却して、漸く今回の軽井沢行が終了しました。
因みに、新型アルファード8人乗りのレンタル料は、ガソリン代を除き3日間で8万6千円でした。そのコストが高いか安いかは別として、慣れない、しかも“借り物”という緊張感は常にありましたが、ワンコも含め家族全員が一台で移動出来ましたので、何ともゆったり感じられた軽井沢滞在でした。
無事に我が家に戻って、緊張からの解放感と、ニ週間近く居てくれた孫たちが帰ってしまった虚脱感と、そして何よりも、ジジババにとってはニ週間に及んだ“夏の陣”の疲労感とがないまぜになって、家内と二人で、
「フゥ~・・・、疲れたネ。」
「ウン、・・・帰っちゃったネ。」
それにしても、孫のためとはいえ随分と出費の嵩んだ、ジジババにとってのニ週間に及んだ“夏の陣”でした。
当面は、年寄り二人での耐乏生活が続きそうですが、今度また孫たちが来てくれる時までに、例え粗食に耐えてでも何とかまた予算を確保しておかねば・・。
婿殿が横浜から来るので、今回も事前に個室での料理を予約してあった、松本市中町の“季節の郷土料理の蔵”「草菴」。
季節のコース料理も、事前に「7,150円コース(税込) / 9品」を次のコース内容で予約してあり、
・先付 / 2品
・前菜 / 季節の前菜盛合せ
・お椀
・お造り / 旬魚のお造り
・焼物肉
・焼物魚
・蕎麦
・デザート
この内、値段は当然アップするのですが、婿殿と娘の好物でもあるので、信州らしくお造りを馬刺しに、また〆の蕎麦をお椀からざる蕎麦に今回も変更して貰ってありますので、コースとしては概ね8000円位になったでしょうか。
やはり昨年10月末にも伺ったのですが(第1942話)、その時に後継者問題から事業継承のために銀行の仲介もあって、「草菴」が王滝グループ傘下に入ったと知りましたが、従業員の皆さんもそのままで、依然と比べて料理内容も殆ど変わっていなかったので、これからも県外からのお客さんを信州らしい郷土料理でおもてなしする店として、お連れするのに安心したことを覚えています。
その後、もう一度機会があって予約したのですが、その時は急に婿殿が仕事で来られなくなったた、め恐縮ながらキャンセルをさせて戴きました。
実は今回も婿殿が病院勤めのため致し方ないのですが、予定が変わり松本には来られなくなり、最後二泊三日で予定している軽井沢へ迎えを兼ねての合流となってしましました。しかし前回も直前でキャンセルしていたこともあり、今回はキャンセルせずに一名減でそのまま伺うこととした次第です。

 時間通りに着いて、一階フロアへの中町からではなく、小池町側の二階席用の入り口から靴を脱いで入店。子供が這い回ってもイイ様な、お願いしたいつもの畳敷きで椅子席の個室です。
時間通りに着いて、一階フロアへの中町からではなく、小池町側の二階席用の入り口から靴を脱いで入店。子供が這い回ってもイイ様な、お願いしたいつもの畳敷きで椅子席の個室です。先に子供たち向けに、玉子焼きとモロコシのかき揚げ、そしてトマト好きの彼等なのでトマトのお浸しをオーダー。子供たちも美味しそうに食べてくれました。
この日の季節の料理の懐石コースは、先付が二品で、先ずトマト豆腐など。続いて、夏らしく稚鮎の唐揚げとトウモロコシのかき揚げ。稚鮎の苦みがナントも言えません。




そして焼物として、先ずは信州牛のイチボ。柔らかくて塩とワサビが合います。

最後は〆のざる蕎麦。王滝傘下には小木曽製粉所という自社の製粉工場があり、以前より蕎麦が細くなった気がしましたが、市内の蕎麦専門の有名店にも劣らぬ美味しいお蕎麦でした。因みに最後のデザートは桃のジェラートだったか?梨だったか?で、奥さまへ。以上がこの日の9品の懐石コースでした。


予定が変わり、婿殿が松本には来られずに、迎えを兼ねて最後の軽井沢で合流となったことから、彼が行きたいとのことで当初予定していた「白馬岩岳マウンテンリゾート」は次の機会に回して、今回孫たちを連れて行ったのは、塩尻峠の山麓に在る農業公園「チロルの森」です。
 チロルの森のH/P等から拝借すると、
チロルの森のH/P等から拝借すると、
『「信州塩尻農業公園チロルの森」は、ワールドインテックが運営する、欧州オーストリア・チロル地方をモチーフとした、標高1,000mにある総合テーマパークです。
ヨーロッパの牧歌的な景観や農業体験などを楽しむことが出来、主な特徴はラベンダー畑や牧舎があって、乗馬や動物とのふれあいなど自然に溶け込んだ施設となっています。
また、本場の製造を元に作った自家製のビールや濃厚なアイスクリーム、ジューシーなソーセージが楽しめます。また、石窯で焼いた本格的なピザやパン。豊富なメニューのレストラン、体験教室など、「見て・触れて・食べて」五感で楽しめる施設です。
しかし来場者の減少と新型コロナウイルス感染症の影響で2020年11月29日に一度閉園しましたが、2025年4月26日に再開園しました。』
再開については、
『長野県塩尻市にある「チロルの森」が、2025年4月26日(土)より営業を再開いたします。本施設は、2020年11月に新型コロナウイルス禍の影響を受け、閉園を余儀なくされました。しかし、多くの皆様から寄せられた温かい支援と期待の声に後押しされ、昨夏にはトライアル営業を実施し、一ヶ月間に約25,000人の来園者を迎えることができました。この結果を踏まえ、4年半ぶりの営業再開を決定いたしました。』

この日は夏休み期間中の平日で、従業員の方と思しき車を除くと、約2000台収容という広大な駐車場に、開園時間での来園は僅か10台足らず・・・。





このエリアには林の中にツリーハウスなどもあって、おとぎの国の様な雰囲気です。


しかし、この日は平日とはいえ、午前中の入園はせいぜい50人程(どんなに多く見積もっても3桁には届かず)ではないでしょうか。勿論、一度閉園しているので、施設やアトラクションの充実にはお金を掛けられず、当面は現状のモノを維持管理していく他はないかもしれません。しかし、信州の高原風の広大な森の中で雰囲気もイイし、都会から来れば避暑地感覚でも楽しめる。なのに、こんなに空いていてはナントも勿体無い。
例えば、入場料は無料ですが、週末になると親子連れで駐車場は満車になるアルプス公園に在るようなドリームコースターか、長い滑り台のロングスライダーなど様々な子供向けの遊具や、或いは安全な子供向けの最近はやりのボルタリングもイイ。園内の林の大きな木々を活かしたブランコやジャングルジムの様な遊具でもイイ。いずれにしても広大な敷地と傾斜を活かすべきだと思います。そして、白馬岩岳ではありませんが、チエとズクで何とか子供たちが喜ぶ様な、是非目玉となる様なアクティビティーを創造して欲しいと思います。例えば、上手く傾斜を活かして“日本一長い”ロングスライダーを設置出来れば、それだけで目玉として“日本一”を売り込めます。

何より、ここにはそうした「チエとズク」の要素となる明るい材料が、広大な森の中に幾つも潜んでいる様に感じるのです。是非頑張ってください!
【追記】
入園者が少なくコストを掛けられないのは理解できますが、園内を色々探しても閉まっていたりしているレストランや施設もあって、結局この日のランチは園内では取るのを諦めて車で戻り、松本IC近くのベーカリーレストラン「COCORADE」で食べました。その分も「チロルの森」は収入減となってしまっているのです。これも実に勿体無い!
何日も実家に居ると、松本での孫たちの“遊び”の材料が次第に“枯渇”して来ます。
都会であれば、動物園や水族館、キッズランドなど、そうした小さな子供たちが喜ぶ施設が幾つも有るのでしょうけれど、田舎ではなかなかそうはいきません。


孫たちの一番人気は、イオンモール松本のキャラクターカートで、特に二人共アンパンマンが大好きで乗りたがりますが、週末などは子供たちのためにパパママたちが競って“早い者勝ち”での奪い合いになります。娘に依ると、
「無料で乗れるなんて信じられない!有料にして貰ってもイイくらい・・・」
とのこと。
滞在中、私は用事があって行けなかったのですが、幼児連れのママさんに優しい「和み」でのランチを今回も個室で予約して、その前後にイオンモールの「キッズリパブリック」で買い物をするために、終末よりも混まない平日に家内と出掛けて行き、しっかりとアンパンマンのカートを確保して二人共乗れた様です。
また、食料品買い出しはスーパーマーケット「ツルヤ」の中南信地区進出1号店でもある「渚ライフサイト」内の「ツルヤなぎさ店」が、ナント1年4ヶ月も掛けて7月から改装休業中(歳を取っても歩いて行けるからと今のマンションに決めたのに、まだ運転が出来る我々は良いとして、そうした事情を抱えたお年寄りは「その間は他店へどうぞ」と云われても、では実際にどうすれば良いのか、余りに“ユーザー・アンフレンドリー”な対応と云わざるを得ません)のため、結果代わりに選んだのが、松本市内の本店を閉めた井上百貨店が運営する、松本市郊外山形村のショッピングモール「アイシティー21」です。今までは殆ど利用したことは無かったのですが、市街から郊外へ向かう道路は混んでいないので、渚からは15分足らずで行くことが出来ます。そして、こちらにも「ツルヤ」が敷地内に別棟で入っています。
たまたま行った日は夏休みということもあって、アイシティーの一階モールの中央ステージで日替わりのイベントがされていて、この日は子供向けの音楽ステージが無料で40分間実施されていました。
ステージ前には椅子席も用意されていて、今回は昼前後の2公演でしたが、出演は大阪市東淀川区に拠点を置く「スキップ楽団」とのこと。
こちらの楽団は1977年に結成された、幼稚園や保育所の遊戯室、高齢者施設のロビーや食堂等、小規模スペースを会場とする公演など幅広い活動をしている音楽集団とのことで、この日はメインボーカル兼アイリッシュハープの女性、3代目リーダーというヴァイオリン、他にキーボード、ドラムスの各々ボーカルも兼ねる男性3人の計4人編成。
ステージは、アイルランド民謡の「ダニーボーイ」や童謡「雨降りお月さん」、そしてジブリのトトロから「さんぽ」などなど。
皆さん音楽の専門教育を受けられたプロミュージシャンの様で、わざとふざけては子供たちを沸かせながらも演奏はしっかりしていますし、女性ボーカルも澄んだソプラノで上手でした。子供たちも手拍子をしながら喜んでステージも大いに盛り上がっていました。
今や音楽大学を出ても、演奏人口の多いピアノやヴァイオリンなどは、著名な国際コンクール優勝の肩書か、或いは技量は“そこそこ”でも余程の美形でなければプロ演奏家として売れることはありますまい。ですので、こうした形で毎日音楽を生業に出来るのは、例え王道ではないとしても、音楽家人生としては或る意味幸せではないだろうかと、へそ曲がりの斜視的な見方かもしれませんが、手拍子をしながらそう感じて私も聴き入っていました。


上の子が電車好きということもあって、“時間潰し”のイベント代わりに二度、マンションからすぐのアルピコ交通(旧松本電鉄)の上高地線の渚駅から二駅の松本駅まで電車で往復しました。
松本と上高地への入り口となる新島々までの上高地線は現在二両連結で、京王電鉄の3000系車両が引退し、現在は東武鉄道20000系車両3編成で運行されています(内1編成が、アルピコ社内の女性社員が描いた上高地線のキャラクター「渕東(えんどう)なぎさ」がCFなどに依って描かれた、2代目なぎさトレインです。因みに渕東も渚も上高地線の駅名)。


大人の我々からするとたった二駅、僅か片道4分の乗車時間なのですが、彼等幼い孫たちからすると立派な“大冒険”なのでしょう。
踏切がカンカン鳴って電車が近付いて来る時から嬉しそうにはしゃいでいて、ドアが開いて乗車し、たった4分間の沿線の様子を窓越しに靴を脱いで座席に正座して眺めながら、終点の松本駅では八王子から乗って来た特急あずさが多い時は4編成も停車していたりと、乗り物好きな子供たちは電車での行き帰りをとても喜んで乗っていました。





